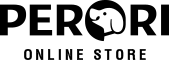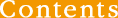獣医師のドッグフード研究コラム
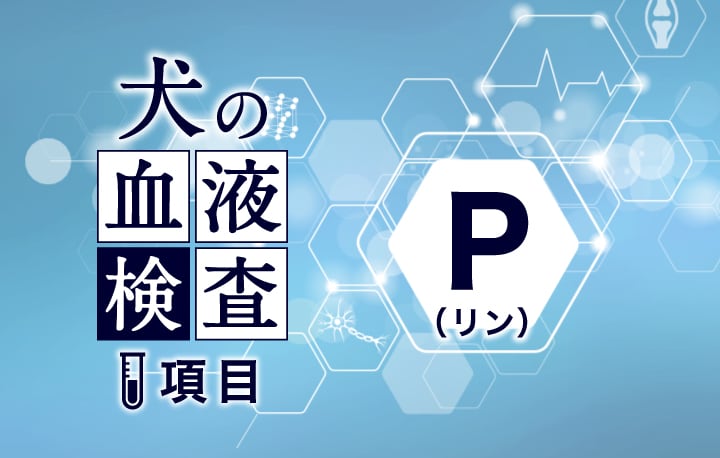
第55回:犬の血液検査項目 - P(リン)-
こんにちは。獣医師の清水いと世です。
今回のコラムは犬の血液検査項目のP(リン)についてです。
慢性腎臓病の際によく検査される項目で、その食事管理に考慮すべき栄養素でもあります。今回はドッグフード選びの注意点についても解説します。
はじめに(この血液検査項目のコラムをはじめてご覧になる方はお読みください)
ここで取り上げている血液検査の項目のみで、愛犬の健康や病気の状態は判断できません。
動物病院では、他の血液検査項目、触診や聴診のような身体検査、そしてレントゲンやエコー検査などを合わせて診断しています。
ここの内容は、動物病院で受けた検査項目の確認や、獣医師から受けた説明の復習にご利用ください。
ネットで情報をピックアップして不安を増やしてしまうより、心配な血液検査結果は、かかりつけの動物病院で直接確認する方が、早めの解決につながります。
リンとは
リンはカルシウムやナトリウムと同じく、体に必要なミネラルの一種です。骨はハイドロキシアパタイトというリン酸カルシウムの種類で主に構成されていて、リンはカルシウムとともに骨に最も多く存在しています。
食べ物でも骨ごと食べる食材にリンは多く含まれており、肉のようなタンパク質にも多く含まれています。
リンとカルシウムはかかわりが深いため、血液検査では、カルシウムの項目も一緒に測定されることもよくあります。
リンの役割
上記したように、体内でリンは骨の構成成分になるほか、細胞膜のリン脂質やエネルギー供給物質であるATP(アデノシン三リン酸)、そして遺伝情報であるDNA(デオキシリボ核酸)の成分にもなっています。このため、体のあらゆるところにリンは存在しています。
また、リン酸イオンは体内の酸塩基バランスを整える役割があり、血液のpHが酸性(アシドーシス)やアルカリ性(アルカローシス)に傾かないように調整する役割も果たしています。
リンの恒常性(一定に保つ方法)
血液検査で測定されるリンの値は、消化管からのリンの吸収量、尿への排泄量、組織(細胞)への取り込み量によって変化します。この吸収量や排泄量などに関与しているのが、上皮小体ホルモン(副甲状腺ホルモン、PTH)やビタミンDなどです。
血中のリンが増えると、腸から吸収されるリンの量を減らしたり、尿への排泄を増やしたりします。逆に血中のリンの量が少ない場合は、腸からの吸収を増やし、尿への排泄を減らして、血中のリンを一定に保つように働きます。
ドッグフードに含まれるリンは植物性の材料より動物性のリンの方が体内に吸収されやすかったり、ドッグフード中にカルシウムのようなミネラルが多いとリンの吸収が阻害されたりします。
リンが異常となる原因
ドッグフードに含まれるリンは消化管から体内へ吸収された後、主に腎臓から尿として排泄されます。ドッグフードに含まれるリンが多くても少なくても、通常、ホルモンの作用などによりコントロールされるため、血液中のリンの値に大きな影響が出ることはありません。
リンが異常値を示す最も多い原因は、腎臓の病気です。腎機能が低下すると、腎臓から排泄されるリンの量が減り、血液中のリンの値が高くなってしまいます。
このほか、ビタミンDの摂りすぎや、組織が破壊されるような病気のために、血液中のリンが増える場合もあります。
一方、リンが少なくなる原因は、リンの摂取不足や、ビタミンDの欠乏、細胞内へのリンの取り込みが増えた場合などがあります。
リンが異常なときの症状
血中のリンが高い状態が持続すると、血管や腎臓などに石灰化といってカルシウムが沈着し、その組織の機能が損なわれてしまいます。
慢性腎臓病では腎臓の機能が低下し、リンの排泄が減るため、高リン血症になりやすく、この高リン血症が持続することで腎臓に石灰化が生じ、さらに腎臓の機能が悪くなってしまいます。
腎臓病の症状はその病気の進行の程度で異なりますが、尿量が増えたり、食欲にムラが出たり、飲水量が増えたり、口臭が悪化したりします。
リンの検査結果が基準値を少し下回る程度であれば特に症状はありませんが、深刻な低リン血症では、溶血といって赤血球が壊れてしまい、貧血のような症状が現れることもあります。
リンが異常の場合は原因究明と治療効果の確認のために追加検査を実施
リンは、健康診断や病気の際の全身のチェック項目のひとつとして、あるいは慢性腎臓病のようにリンの異常が疑われる際に検査されます。
リンの異常が見つかった際には、その原因に食事や慢性腎臓病が関与していないか、食事内容や慢性腎臓病の際に異常となることの多い血液検査項目(BUN、Creなど)を確認したり、尿検査を行ったり、レントゲンやエコー検査で腎臓の形状に異常がないか確認したりする場合もあります。
異常となったリンのために、ドッグフードの変更や、リンを下げるための薬(低リン血症のためにはリンを上げる薬)を使用する場合があります。
これらの効果を確認するために、また、慢性腎臓病のような病気の場合は病気の進行をチェックするためにも定期的に検査が行われます。
異常なリンを改善させるためには原因に応じた治療や栄養管理が必要
慢性腎臓病では、高くなったリンを下げるために輸液の治療を行ったり、リン吸着剤や慢性腎臓病専用の療法食(低リン食)を使用したりする場合があります。
一般的に、慢性腎臓病用の療法食は、総合栄養食のドッグフードよりリンの量が制限されていますが、「腎臓に優しい」や「腎臓に配慮した」総合栄養食の場合、ドッグフードの分類は総合栄養食であり、通常その栄養基準であるAAFCO養分基準を満たすようにリンも十分量含まれていると考えられます。
かかりつけの動物病院より処方された療法食をあまり食べないからといって、愛犬のために探したドッグフードがリンの多い食事にならないように注意しましょう。
ドッグフードのパッケージにリンの量は記載されていないことが多く、病気の際の食事はかかりつけの動物病院で相談しましょう。
リンは骨に含まれる量が多いため、骨を含むおやつは避けましょう。
まとめ
血液検査項目のリンは慢性腎臓病の際に検査されることの多いミネラルです。
慢性腎臓病ではリンを尿から排泄する能力が落ち、血液検査でリンの値が高くなります。
慢性腎臓病の栄養管理では、リンの少ないドッグフードが推奨されます。

獣医師清水 いと世 (京都大学博士 / 農学)
山口大学農学部医学科卒業後、動物病院にて勤務。
10年ほど獣医師として勤務した後、動物専門学校で非常勤講師を務める。
その後、以前より関心のあった栄養学を深めるために、武庫川女子大学で管理栄養士の授業を聴講後、犬猫の食事設計についてさらなる研究のため、京都大学大学院・動物栄養科学研究室を修了。
現在は、栄養管理のみの動物病院「Rペット栄養クリニック」を開業し、獣医師として犬猫の食事にかかわって仕事をしたいという思いを持ち続け、業務に当たる。
- 第1回:犬の食事に含まれる三大栄養素の割合
- 第2回:犬の痒みの訴え
- 第3回:犬にとっての必須栄養素 ビタミンE
- 第4回:犬のてんかん
- 第5回:家庭内に潜む犬にとって危険な食べ物 パート1
- 第6回:家庭内に潜む犬にとって危険な食べ物 パート2
- 第7回:犬にとってのビタミンD
- 第8回:犬の食事の嵩(かさ)を増やす方法と注意点
- 第9回:犬にとってのビタミンK
- 第10回:犬が酵素を取り入れることの意味
- 第11回:犬にとってのビタミンA
- 第12回:犬と乳酸菌
- 第13回:犬にオリゴ糖を与えて期待できること
- 第14回:犬の熱中症の怖さと対策方法
- 第15回:愛犬の食欲が少し落ちたときにできること
- 第16回:犬に必要な栄養素 チアミン(ビタミンB1)
- 第17回:ドッグフードを変えると同じカロリーでも太っちゃうわんちゃんへ
- 第18回:犬の心臓病 うっ血性心不全
- 第19回:犬に必要な栄養素 リボフラビン(ビタミンB2)
- 第20回:犬の胆泥症 <前編>
- 第21回:犬の胆泥症 <後編>
- 第22回:犬に必要な栄養素 ナイアシン(ビタミンB3)
- 第23回:犬にグルテンフリーの食事は必要ですか?
- 第24回:犬に必要な栄養素 - ビタミンB6 –
- 第25回:犬に穀物は必要?
- 第26回:犬に必要な栄養素 -パントテン酸(VB5)-
- 第27回:ドッグフードと犬の拡張型心筋症の関係
- 第28回:犬に必要な栄養素 – 葉酸(ビタミンB9) –
- 第29回:犬に必要な栄養素 – ビタミンB12 –
- 第30回:ドッグフードがない!そんな時のドッグフード代わりの今日だけ手作り食
- 第31回:犬に必要な栄養素 – コリン –
- 第32回:犬に必要な栄養素 カルシウム(Ca)
- 第33回:犬のストレス
- 第34回:犬の尿路結石 -前編-
- 第35回:犬の尿路結石 -後編-
- 第36回:犬の日光浴
- 第37回:犬に必要な栄養素 リン(P)
- 第38回:犬のよだれが多いとき
- 第39回:犬に必要な栄養素 マグネシウム(Mg)
- 第40回:犬に必要な栄養素 -ナトリウム(Na)と塩素(Cl)-
- 第41回:犬に必要な栄養素 -カリウム(K)-
- 第42回:犬に必要な栄養素 -鉄(Fe)-
- 第43回:犬に与えていい食材と危険な食材について
- 第44回:犬に必要な栄養素 -銅(Cu)-
- 第45回:犬に必要な栄養素 - 亜鉛(Zn)-
- 第46回:犬に必要な栄養素 - マンガン(Mn)-
- 第47回:犬に必要な栄養素 - セレン (Se) –
- 第48回:犬に必要な栄養素 - ヨウ素(I)-
- 第49回:犬の血液検査項目 ‐ ALT(GPT)‐
- 第50回:犬の血液検査項目 -BUN(血中尿素窒素)-
- 第51回:犬の血液検査項目 -AST(GOT)-
- 第52回:犬の血液検査項目 -Cre(クレアチニン)-
- 第53回:犬の血液検査項目 -Ca(カルシウム)-
- 第54回:犬の血液検査項目 -GLU(グルコース・血糖値)-
- 第55回:犬の血液検査項目 - P(リン)-